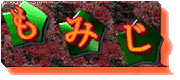
| 「赤いね」 「うん」 「黄色いね」 「うん」 「いつから」 「こないだ。ほら、急に冷えたとき」 「痛かった?」 「ううん、かゆかった」 「いつから」 「こないだ。ほら、強い風んとき」 「緑飛ばされちゃったんだ」 「ヒューってね」 「どこいったんだろう、僕たちの緑」 「最初は夕焼けで赤いのかと思った」 「最初は月明かりで黄色いのかと思った」 「風出てきたね」 「うん」 「冷たい風、やだな」 「うん。でも、強い風の方がもっといやだ」 「飛ばされちゃうかも」 「空高く飛ばされたら、星になれるかな」 「川に落ちたら、海に流されてそこで海星ヒトデになるんだって」 「ふーん、海の中にも星ってあったんだ」 「なんか、近くに変なのが、沢山ぶら下ってるんだけど」 「あれは、種だって」 「種」 「僕たちの仲間みたいだよ」 「何であんな格好してるの」 「あの羽みたいなので風に乗って、くるくる回って、遠くまで飛んでくんだって」 「飛ぶとこ見れるかな」 「一緒に飛べるかも」 「物知りだね」 「近くにある木にいる緑の葉っぱが、いろいろと教えてくれるから」 「じゃあ、緑の葉っぱが物知りなんだ」 「うん、緑の葉っぱは落ちないんだって。色も変わらないし」 「僕たちと違うの?」 「そうみたい。僕たちが生まれるずっと前からここにいて」 「ここにいて」 「僕たちがいなくなっても、ずっといるんだ」 「長生きなんだ」 「うらやましい?」 「うらやましいのかなぁ」 「少なくなったね」 「ほとんど飛んでっちゃったね」 「中には、そのまま落ちちゃったのもいるけど」 「僕たちがいなくなっても」 「もうじきかな」 「うん。今しがみついてるこの木は残って、またいつか葉っぱが出るんだって」 「ひょっとしてその葉っぱも、赤くなったり黄色くなったりするのかな」 「同じことの繰り返しだって」 「じゃあ、また僕たちが出て来たりして」 「そうなれば、楽しいね」 「それにしても、この木はしゃべらないのかな」 「年寄りだから、もうしゃべる元気は残ってないみたい」 「そうか、でも僕たちの話は聞こえてるよね」 「どうして」 「お礼ぐらい言っといた方が、良いんじゃないかと思ったんだけど」 「ついでに、この次の事も頼んどこうか」 「この次の事?」 「また僕たちをこの木につけてくれるようにって」 「覚えてるかな」 「何を?」 「またこの木についたとき」 「ついたとき?」 「自分のこと、星になること」 「覚えてるかな」 「ふと思ったんだけど」 「これが初めてじゃないかも」 「先に言われちゃった」 「でも、前の時のこと覚えてないね」 「じゃあ、初めてなのかな」 「空、ものすごく高いね」 「ものすごく青いね」 「雲、真っ白」 「雲、あんなにやせちゃって」 「何か、吸い込まれそう」 「川が、キラキラ」 「水、けっこう流れてるね」 「ホントに、海につながってるのかな」 「海、見たことないね」 「あっちの、空が地面にくっつきそうな所」 「えっ、あの空ものすごくキラキラしてる」 「あれが海だって」 「雲が、すごい勢いで出来たり消えたり」 「あれは、雲じゃなくって波なんだって」 「忙しそうだけど、おもしろそう」 「今日は鳥あまり見ないね」 「風が強いからね」 「お日様暖かくて気持ちいい」 「うん、ポッカポッカ」 「雲があんなに伸ばされてく、あっ、ちぎれちゃった」 「ホントだ、ちぎれた方、もう消えちゃったね」 「ねえ、川を見て、仲間が流されてくよ。海で星になるんだね。ねえったら」 「あれっ」 秋は、流れゆく雲のように駆け抜け。 容赦なく、すべての色を洗っていく。 青はより青く、白はより白く。 すべての色は、透明な光の前におのが姿をさらけ出す。 空気さえも洗われる、そんな日。 冬はもうそこに。 |
Copyright ©1999-2026 gosadon All rights reserved