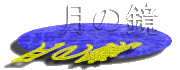
| 残照を浴び、辺り一面の芒 すすき が風に泳ぐ。 その身の丈ほどをかき分け四方より現れ出るは、四ったりの影。 して、やがて四ったりが落ち合うは、まさに、そこのみ芒の円形に丁寧に刈り取られ、 あるいは更に辺りの芒、放射状に渦巻き押し倒されている所。 かの所、更に眺めんと欲すれば真中に一尺ばかりの穴の地に空きたる。 異様なる装束 しょうぞく を纏い まとい 、様々な物持ちたりし者共、すなわちかの地にて出会う。 やがて、相手を認むるにその顔に笑みぞ浮かぶ。 挨拶の無き内に、北方より来る者、手中の巻物広げ読み始む。 「・・・・・・かようにして、場所を決めたる後。 地中に経五尺の完全なる球を作り、その内側を錫 すず にて隙間無く覆うべし。 ただし、地上に経一尺の正円なる開口部を設けるため、地中の球の心は、 若干浮かすべし」 南方よりの者答えて曰く。 「まさに、違 たが わず」 東方よりの者。 「既に、かように穴のありしこと、まさにその証 あかし 」 「然 しか り」 とは、西方よりの者。 そにかまわず、北方よりの者続け読む。 「白露 はくろ 後の最初の満月の時」 いずれかの者、詠 えい す。 「時は来たれり」 「時は満ちた」 「然り」 答えて曰く。 「では、いざ始めなむ」 「おうとも」 この声もちて、三者すなわち東、南、西から至れる者、 重き荷を解きて、仕度に取りかかる。 その仕度の多きこと、知るに違わず。 北より至れる者、黙して動ぜず、ただ、そを眺むる。 ただちに日は落ち、辺りを照らすは件の十五夜、宿する星のみ。 目鼻かろうじて認めん月明かりの中、北方より至りし者、いつしか続け読み始む。 この明かりにて、そを読み続ける事、まさに一言一句諳 そら んじているに他ならず。 その低き声、そよぐ風に乗りかつ虫の声に紛れ、そこかしこに降り注ぐ。 あたかもその様、かの月明かりの如し。 「春分、夏至、秋分、冬至に、日の出より集めし月の雫 しずく もちて、 正円の器に等量入れ置く 更にそれを白露の月の雫にて半分に希釈す」 他の者、かの詠に応じ舞を始む。 しかれども、楽に舞うは、三者にあらず。 楽に踊るは、その持ち来る物のみ。 やがて、かの器折々の月の雫にて満たされ、そは無言にて揺蕩 たゆた う。 すでに、夕陰草 ゆうかげぐさ はうち臥 ふ し、夕烏 ゆうがらす こそ何処へ。 さすれど、声は依然続く。 「地の方、球の心違えることなく、 五尺の大なる方格規矩鏡 ほうかくきくきょう 伏し置き、 鈕 ちゅう にかの器を置く」 あたかも、かの十五夜そを正面に見るが如く天頂にさしかかりつ。 「器の四方、則ち、、坎 かん 」 坎と発するに時を移さず、北より至りし者、半歩前へ進み出ておのが位置に着き、 三ったりを見回し先を続けむ。 「震 しん 、離 り 、兌 だ に術者を置き、然るべき時を待つこと」 そが声を聞きし、東より至りし者、 「震とはまさに吾が事なり、かが指すが雷の事なれば、異を唱えずが」 かく宣 のたま いて、位置に動く。 「離なるは吾が事なり、火、日。明るきことは吾 われ に」 と宣いて、南より至れし者その身を南へ。 「兌、すなわち沢を表す」 かく呟きたるは、西より至りし者、そが場所に動いてから後。 暫しの間をおきて、全ての仕度整いし事見届けたる後、 坎なる者、正面を向きて、月を望み位置を測りて、黙して語らず。 あたかも月、天の頂にさし懸 か からんとする正に前、坎なる者、再び唱えるを始む。 他の者、かの声の始まるを聞きて、畏 かしこ まりて時を待つ。 辺りに動く物あらざりき、そが声、かの月除きては。 やがて、坎の声かく唱えるに全ての者共色めき立ちて、これに従う。 「月まさに天頂に懸かるとき、 それを水鏡ともってし、 そを捕らえ、月の鏡とす」 すなわち、三ったり、三つの方から先の器にて時を計る。 三者いずれも時を同じくかく哭 おら ぶ。 「まさに、いまがその時」 坎その声待つことなく、先を詠す。 「月逃げんと欲する前に、素早く、凍結すべし」 あるいは三者、これもその声待つことなく、自ずから呪の文言 もんごん を唱う。 やがて、眼下の月真に凍てつけど、そが光放つを止めず。 器より漏れし光り、大なる圧となりて、四ったりの術者を襲う。 かの三ったり、なんぞ感ずることなくかく曰う。 「なにごとぞ、起こりけむ」 「うむ、御し難しとはこの事ぞ」 「かくなること、かねてより承知の故」 「然り、然れども」 「我らが道、違わくばかような道、如何にしておこりけむ」 「されど、我らが力及ばず、かのごとき事招き寄したるが時」 「さするときのみぞ、遮莫 さばれ と曰うがよし」 「我が意、存ずる限り、かようなこと宣いけるに」 「詮方 せんかた なき事よ」 この時、何れかの者宣う。 「いまぞこそ、かくがごとき曰いけずに、かの文言曰いけるに」 あたかもその言、陽の明かりのごとし。 いずれ、かの者共の戯 ざ れ言止まり凍てつ。 されど、その言誰の口より出しかは、今となりては、知る由もなし。 そは言の葉の元、坎を持ってしても知る由を叶わず。 しかれども、かの時、言止まりしと思いける者、何処にぞおらん。 また、捕らわれし月の明かりも、かく思うべし。 尚、凍てつくは彼等が言に止むにあらず。 いつしか、かの明かり絶えることなく続く詠に誘われ、球におさまりけむ。 まるで、そは、おのが意に従うがごとし。 唯一これを感じし者ありき。 坎、これ一切を構わず、唱うを続けむ。 これすなわち、唱うを止むはこの世の終わりと心得けるに他ならず。 「捕らえた月、触れることなく、 上下を違わぬ様、器より出し、 先の球の心に置く」 その間、断なく続く低き声、皆をもって励し援ず。 「その後、再び方格規矩鏡伏し置き、 その上に、四人の術者、本来と対の位置に乗りて、 飛翔詠唱うべし」 かく宣いて、坎巻物を終う。 月明かり、見事にかの場所に押し込められたるも、 依然として、光放つを止めず。 そは、青銅の鏡貫きて、あるいは鏡自らを光らせつ、けっして、絶えること無し。 いずれの者も、身体に汗し、頬は削 そ げおちたるも、 足下 そっか よりの強き光にて、認むるを叶わず。 四ったりの者共、暫時顔を見合わせ互いの意を認めたるが後、 鏡を心に、右より廻 めぐ りてその位置に着く。 すなわち、北の者、南へ、東の者は西へ。 しかる後時を置かず、心して飛翔詠声を合わせ唱え始めん。 やがて、一時はその、時には高くまた時には低く流るる声に応じ、脈動せしかに憶 おぼ ゆかの光、 何処かで再び、おのが在りし姿見出し足るが如く、突然として自ら動き出したるは、 彼等をもって、尚知る術もなし。 この時すでにかの青銅の鏡、内なる力によりて、まさしく、はち切れんとす。 そは姿、まるで今にも火を噴 ふ きたるが山の如く。 それより出たる、光と熱、陽を喰らい給うと思うが如し。 その姿、あるまじき理 ことわり にあらずといずれも思いけるが、 あえて、この際に及びて口出す者なかりけむ。 否、それぞまさにこの時にかような事口に出せるは、この世の者にあらざりき。 而 しこう して、かの四ったりそれを語らず、唱うるを続くのみ。 彼等が今の心の内、いずれの者を持ってしても知る術 すべ 無し。 そを待ち受けたるは、世の理のみ、他を持って知るを叶わず。 すなわち、大いなる光と音持ちて、かの青銅の鏡その心より裂けたるが、 かの四ったり、そに弾 はじ かれ舞いて心何処へ。 尺なる穴より月の明かり漏れ出て、空を割き、天に昇りけるも、 そを認むはいずれの者にぞ。 後に残りしは、尺なる穴に揺蕩う件の雫のみ。 かの雫、月の名残か妖しげに美しき燐光放ち続けむ。 さすれど、辺りこれを除きては、普段と変わらぬ景色なり。 これに恥じたか、四ったりはいずれかに隠れその姿を見せず。 このときすでに、満ちた月は西に傾き、まさに沈まんとす。 すなわち、新しき陽昇るを、ただ待ち願うのみ。 やがて、かの時を迎え、かの時を送る・・・・・・ ・・・・・・そしてまた、時を迎える。 「皆、目を覚ましたか」 「何が、おきたんじゃ」 「結局は、御し損ねたのでは」 「やはり、でも何故」 「それより、身体は」 「身も心も、変わりはない」 「それは、なにより」 ある者は、首に手をやり、ある者は頭を抱え、ある者はまた辺りを見回す。 姿の見えない互いを気遣い、叫び合うその声は力無い。 「年に一度の名月の宴」 「まさに祭りとはこの事」 「無事で何より」 「そうだな、無事なのはまさに奇跡とでも言うか」 いつの間にか喚き始めた虫の声に気圧されてか、月は天頂から静に降りようとしている。 「見ろ、あの月を」 「月がどうした」 「痩せておる」 「何故」 「それは、我らが月の力を奪ったためか?」 「よく見てみろ。満月も、一日経てば十六夜に」 「十六夜?、確かに」 「すると我らは、一日中?」 「かような事。一日で済んで、感謝せねば」 「それよりも、穴は」 昨夜と同じように、四人は四方から集まってくる、 ただし今回は、先と反対の方向から。 目指すは、同じ場所。 ただし、その足取りはうって変わりおぼつかない。 やがて、穴の放つ燐光が、互いの姿を浮かび上がらせる。 皆その手に四半円状の者を提げている。 互いの無事を確認しながらも、無意識のうちにその目は穴へと。 「おぉ、まだ、光っている」 「妖しくも美しい」 「で、中は」 「まぁ、そう急くでない」 「どれっ」 「でっ、どうだ」 「光る水だけだ」 「やはり、うまくいかなかったのか」 風が動き。虫の音が止む。 四人は穴に辿り着き、それを囲むように座り込む。 一瞬の沈黙。やがて皆の目はいつしか月へ。 「無謀はもとより、覚悟の上」 「それにしても何故」 「たぶん、我らの心が一つになりきれずに」 「なんだと、あんなにピタリとあっていたのでは」 「合っていたのは、その息のみよ」 「何をもってそう思う」 「皆の手の物を見るが良い」 「これか、ワシのすぐそばに転がっていた」 「ああ、多分コレが頭にでも当たったんじゃろう」 「鏡がどうしたと」 「見事に四つに裂けている」 「それが」 「それが、何よりもの証」 「謎掛けはもう良い、早く話せ」 「例えばだ、まさにその時何を思っていたかだ」 「いまさら何を」 「飛ぶことに決まっておるじゃろ」 「それ以外に何を」 「では重ねて聞く」 「どこへ」 「どこへじゃと」 「そう、どこへ飛んで行くつもりだったんじゃ」 「うむ、そう言うことか」 「飛ぶことのみ考えて、行く先を考えなかったということだな」 「まぁ、そのようにして、実際我々はこのように飛ばされたわけだ、 それを考えると、あながち失敗したとは言えんぞ」 「まさに、然り」 「すると今度は気を付けねばな」 「おまえ、またやるつもりか」 「やらないのか」 「今はわからん」 「懲りない者共だ」 「はっはっはっ」 「ところで離よ、もし飛べたとしたら、どこへ行きたい」 「確かに、ワシはただ飛ぶことに夢中で、行く先は考えておらんかったなぁ。 さて、竜宮で乙姫と逢瀬というのは、どうじゃ」 「はっはっ、おもしろいことを。竜宮は海の中ぞ」 「おう、そうか。では黄泉比良坂 よもつひらさか の筍が食べ頃だと聞くが」 「おぃ、おぃ。それは地の中じゃ。おまけに場所もわからん」 「場所もわからぬで思い出したが、蓬莱国 ほうらいこく 、方丈国などを探して、 神仙と酒を酌み交わすというのは」 「場所がわからぬと言うのなら、この世の果ての果て、つまりこの世界の終わりに、 海が滝となり、奈落へと落ち込む場所があるとか」 「ほう震は、物知りじゃなぁ」 「坎にはかなうまい、坎はどうなんじゃ、どこへ行きたい。 それともかの時、すでに念じていたか」 「いかにも、ワシはすでに決めていた。念じていた」 「では何故かの時」 「おぃ、震よ。もう過ぎてしまったこと、いまさら何を言ったとて」 「離よ、いいのじゃ。全てはワシの責任じゃ、すまない。 だが、それに気が付いたのは、今さっき。 ふぉっふぉっ、大方鏡の当たり所が良かったのじゃろうて」 「いや、それはこちらこそ、すまなんだ。 して、坎は一体どこへ行きたかったのじゃ」 いつの間にか、虫の声が戻っている。 風が出てきたのか、ススキが風にそよいでいる。 兌は、というと。語り合う三人に背を向け、 一心不乱に自分の荷物をまさぐっている。 「ワシはな、明日へ行きたかったんじゃ。 明日を見たくてな」 「明日だと、一晩寝れば簡単に行けるではないか」 「かような近くの明日ではない。もっともっと、遠い先じゃ」 「例えば」 「例えば、百年。例えば、千年。ワシ等がとっくにこの世を去って、更にその後。 ひょっとしたら、人さえも・・・・・・。そんな明日じゃ」 「はっはっ、何とも酔狂な」 「ふぉっ、今となっては、ワシもそう思うぞ」 「兌よ、兌はどうじゃ」 「おい、何をしてるんだ」 「まぁ、ちょっとな。おぉ、こんな所に」 「それは、つるべ、なぜ」 「いや、もしその前に雨が降って、穴に水が溜まったらと思ってな」 「いつもの事ながら、兌は準備が良いな」 「ところで、そのつるべ、どうするのじゃ」 「知れたことよ、このままではあまりにも悔しいのでな、ほらっ」 兌の投じたつるべは、穴の中へ。 つるべが上がるに連れ、中の錫張りに反射してか、青白い燐光が、一層妖しく光る。 やがて、つるべは兌の足元へ。 他の3人が憑 つ かれたように、その光に見入る中、 これまたどこより取り出したのか、柄杓 ひしゃく が兌の手に。 そして止める間もなく、兌はその光る水を一息に飲み干す。 「兌よ、おまえなにを」 「気は確かか」 「早く吐き出せ」 慌てて兌の元に駆け寄る一行が心配そうに見守る中、 やがて兌の顔が上気してくる。 「うまい、こんなうまい酒飲んだこと無いぞ。どうだ、皆も一杯」 「なんと、呆 あき れたことを」 「本当に、大丈夫なのか」 「よし兌よ、ここまで来たら一蓮托生、どれ、ワシにもよこせ」 「ふぉっ、ワシもつき合おうぞ」 「そうまで言われたんじゃな。さあ、こちらにも」 「おぉ、これは本当にうまい」 「うむ、甘露 かんろ とはまさにこれを指したのでは」 「とろけるようじゃのぅ、心から暖まる」 「よし、一日遅れの月見といくか」 「辺りは一面のススキ、月見には絶好の場所だ」 「はて、面妖な。あんな所に竹藪なんぞあったか」 「どれ、むっ、確かに」 「ははっ、今は竹の春。竹が一晩に二尺や三尺伸びるのは珍しくもない、 ましてやこの月夜、一夜にして藪が出来ても」 「まさに、然り、然り」 「そういえば、町の方も何か妙に明るいな、こう、ぼうっと光っておるぞ」 「はっはっはっ」 「何がおかしいんじゃ」 「光っているのは、ワシ等の方だ」 「おぉっ、本当じゃ」 「おまけに、なんかこう身が軽くなったような」 「ふぉっ、確かにワシ等浮いておるぞ」 「飛ぶとまでは行かぬが、これも月のおかげか」 「これはいかん」 「どうした」 「浮きすぎたせいか、つるべの縄が、足りなくなってきた」 「おっつけ、元に戻るじゃろう」 「それまで、待てんわ」 「ワシも待てぬぞ。よし、ワシの帯を貸そう。 体がこんなに火照ってるんじゃ、装束なぞもういらぬ」 「よし、ワシのも貸そう」 「それにしても良い月夜じゃ」 「はて」 「今度は、どうした」 「なにやら、星の並びがちとずれているような」 「なに、いつもと変らんぞ。さては、主、飲み過ぎか」 「おい、藪の向こうを見てみろ」 「ぬっ、何じゃ」 「町の方さ、光が蠢 うごめ いている」 「おぉっ。あれは、鬼火の群じゃな」 「白、赤、黄、緑。鬼火にこんな様々な色があるなんて、知らなかったな」 「真四角な岩のような城も沢山見えるぞ」 「ふぉっふぉっ、良い酒じゃ。 身体、心のみならず、目まで極楽へ導いてくれるのか」 「極楽か、それにしては殺風景すぎるぞ」 「はっはっ、然り、然り」 「ふぉっ、どうしたことじゃ兌よ。お主、身体か透けておるぞ。 飲み過ぎではないか」 「これは、いかに。そう言う坎殿こそ、透けておられるぞ」 「殿はやめてくれ、殿は。ふぉっふぉっ。 震に離もこんなに間近でそう光られると、眩 まぶ しいぞ」 「そう言う主が、一番眩しいぞ」 「おぉ、これはワシの禿頭 はげあたま を月が照らしてるだけのこと」 「はっはっ、早くも陽が顔を出したのかと思ったぞ」 「はっはっはっ」 「だれぞ、早くつるべを降ろせ」 「おぅさ、まかせろ」 「よし、決めた。来年はあの月を目指すぞ」 「乗った、月を目指そうぞ」 「すぐに秋分、月の雫集め怠 おこた るな」 「鏡も作り直さねばな」 「また忙しくなる」 「ぶわっはっはっはっ」 「なんと気持ちの良い事じゃ」 「然り、然り」 やがて、月も沈み。 暫くして、東の空にそれを追うように、小さく仄 ほの めく見知らぬ四っつの染みのような点が。 だが、それも瞬く間に東雲 しののめ にうち消され、明け残ることもなく。 空き地に、捨てられた四っつの金属片に光があたり、日の出を教える。 そして、そこにはいつもと変わらぬ夜明けが。 秋の朝が始まる。 |
Copyright ©1999-2026 gosadon All rights reserved